車の疑問
[掲載日:2020年2月25日][最終更新日:]
ハイブリッド車とは? 仕組みやメリット・デメリットを徹底解説
いまや特別意識することなく使えるところまで進化
「ハイブリッドカー」「ハイブリッド車」という言葉、世間での認知は広がっているものの、具体的に「ハイブリッドカーってなに?」と聞かれて即答できる人はそこまで多くないのではないでしょうか。
どのような仕組みで動く車で、どのようなメリット・デメリットがあるのかを今回はご紹介したいと思います。
 この記事の執筆者
この記事の執筆者
自動車専門ライター 高田 林太郎
ふたつの動力源を組み合わせたものという意味で使われている
もともとハイブリッドとは、複数のものを組み合わせる、という意味を持つ言葉です。
たとえば、以前取材したことがあるのですが、ガソリンエンジンをベースにタクシーなどの燃料として使われているLPGも使えるようにしたシステムを開発した会社は、それをハイブリッドフューエルシステムと呼んでいました。
この言葉が一般的になったのは、トヨタが初代プリウスを発売した1997年、そのシステムをTHS(トヨタ・ハイブリッド・システム)と名付けたのがきっかけとなっています。
それ以来ハイブリッドというのは、エンジンとモーターを組み合わせたもの、というイメージとなりました。
現在では各自動車メーカーのいうハイブリッドは、すべてエンジンとモーターを組み合わせて走行する、というものとなっています。
これは国産メーカーだけではなく、輸入車ブランドも同じです。
最近のハイブリッドカー事情
最近では省燃費という面ではなく、モーターの持つ回転当初から最大トルクが発生する、という特徴を活かし、より俊敏な走りを実現することを目的として、スポーツカーへのハイブリッドシステムの採用例も増えてきています。

極端な例を挙げれば、ル・マン24時間レースを連覇したトヨタのレーシングカー、TS050ハイブリッドは、その名の通りハイブリッドシステム搭載車です。
またフォーミュラ1も、エンジンに加えてエネルギー回収システムとモーターを搭載しています。そのため現在では、動力発生源のことをエンジンではなく、すべてをまとめて、パワーユニットと呼んでいます。
以前は特別なものだったハイブリッドシステムですが、いまではごく当たり前に使われている、普遍的なものとなったのです。
ベースにあるのは省燃費とコストダウンのせめぎ合い
現在、ハイブリッドシステムの主な方式としては、エンジンで駆動しつつモーターがその走行をアシストしてくれる、パラレル式ハイブリッドと呼ばれるものと、プリウスなどで採用されている、エンジンとモーターをシームレスに切り替えることで走行できる、シリーズパラレル式ハイブリッドと、日産のe-POWERのように、エンジンで発電機を回し、そこで生まれた電力でモーターを駆動して走行する、シリーズ式ハイブリッドが存在しています。
基本的な方式である、パラレル式ハイブリッドは、シンプルなためにコストが抑えられるというメリットがあります。
スズキなどが採用しているマイルドハイブリッドというのもパラレル式ハイブリッドで、通常はエンジンなどが必要とする電力を発電するオルタネーターを強化することで、モーターとしても利用してエンジンのアシストとして使うシステムです。
ひとことでハイブリッドといってもこのようにさまざまな方式がありますが、その大きな目的となっているのは、省燃費という部分となります。
各自動車メーカーは、省燃費を目指しつつ、販売価格を抑えるべく、よりベターなものを採用しています。
その燃費性能は、同じモデルのガソリンエンジン車と比べると、1.2倍から2倍走るようになっています。
たとえばスズキのアルトでいえば、エネチャージなしのF(5速AGS)の燃費は、JC08モードで29.6km/Lですが、エネチャージがついたX(CVT)は37.0km/Lとなっています。
走行距離にもよりますが、これだけの燃費差があると、車両価格の違いを差し引いてもハイブリッド車のほうがお得、となりそうです。
ハイブリッド車のメリット
ハイブリッド車のメリットは、前述したように燃費の良さというのが一番になります。
さらに、環境性能に優れているというのも大きなポイントです。
現在は各種税金の減免措置がありますので、その部分でもメリットを感じられます。
ハイブリッド車のデメリット
ではデメリットにはどんなものがあるのでしょうか。
まずひとつ目は、車両価格が高い、という部分があります。
ハイブリッドではない同モデルと比べると、どうしても割高になるのは、モーターをはじめとする装備が増えてしまうためです。
ただし、税金関係の減免措置や燃費の良さから、多少は吸収できるという面もあります。
次に挙げておくのは、修理や万が一の事故のときです。
ハイブリッドシステムは高電圧を使っています。そのため修理作業などをする際も、一般的なエンジン搭載車とは違い、絶縁工具や保護衣などの使用や着用が必要となります。
そういったものも含めて、修理に手間がかかったり、修理費用が割高になる可能性があります。
ハイブリッド車の大きなポイントであるバッテリーも、劣化をしたら交換することになりますが、その費用は高額です。
当然自動車メーカーはバッテリーの劣化を抑えるためにさまざまな措置を施していますが、しかし可能性がゼロというわけではありません。
そういうこともありうる、と想定しておく必要があるでしょう。
とはいえ、いまや一般的となっているハイブリッド車ですから、日常使用でとくに大きな問題が出ることは、ほぼないといえます。
その上で、減速時は回生ブレーキシステムがメインとなるため、消耗品であるブレーキパッドの減りが極端に少ないなど、長く使っていると気が付くメリットもあります。
そういった諸々を含めた上で、メリットが上回ったと感じた人がハイブリッド車に乗っているという現状です。
ボディタイプ別の
おすすめハイブリッド車を紹介
コンパクトSUVで人気なのは、ヤリスクロスとヴェゼルです。ボディの全⾧は短く、視点が高いので運転のしやすさは一級品です。
フォレスターのe-BOXER搭載モデルはラフロードも苦にしない走破性を持っています。
エクストレイルは、メインはシティユース、週末はアウトドア、という人にぴったりです。
ステップワゴンは、広い室内と低床設計による乗り降りのしやすさが魅力のホンダの人気ミニバンです。以前の「わくわくゲート」は廃止されましたが、使い勝手の良さは健在。
トヨタのノア/ヴォクシーは、ミドルクラスの定番。ノアはバランス重視、ヴォクシーは個性的なデザインが特徴です。
日産セレナはe-POWER搭載モデルなど電動パワートレインが魅力で、快適性や安全装備も充実しています。
アクアはトヨタのハイブリッド専用コンパクトカーで、現行モデルは低燃費に加え、電動4WDの設定や静粛性の高さも魅力です。
フィットは、e:HEV(ハイブリッド)モデルが中心となり、日常使いに優れた視界や広さ、使いやすいインテリアが好評です。
ノートはe-POWER専用モデルとなり、モーターならではの滑らかな加速と燃費性能が特徴。最新モデルは静粛性も改善され、快適性が向上しています。
軽自動車でハイブリッドモデルといえば、現在スズキが有名なところです。ダイハツもDNGA(ダイハツ・ニュー・グローバル・アーキテクチャー)を採用したハイブリッド車である新型タントをデビューさせました。軽自動車にもハイブリッドの潮流があるのです。
プリウスはハイブリッドの代名詞ともいえる存在で、現行モデルはデザイン性と走行性能の両立が魅力です。
MAZDA3 SEDANは、美しいスタイリングと上質な内装、走りの良さが光る一台。ガソリン・ディーゼル・マイルドハイブリッドと多彩なパワートレインも選べます。
アコードは、2モーターハイブリッド「e:HEV」を搭載し、EV・ハイブリッド・エンジンドライブを自動で切り替えることで、燃費と走りのバランスを高次元で実現しています。
月々5,500円~から新車に乗れる「ニコノリ」
国産全メーカー・全車種取り扱いOK

カーリースについて、もっと詳しく知りたい!
という方はこちらをクリック♪
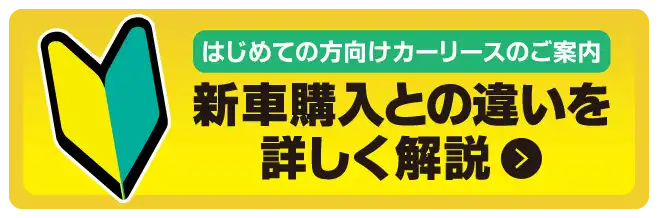
今回はハイブリッド車についてご説明してきました。
ここで私ども、ニコニコカーリース(ニコノリ)について少しご紹介させてください。
ニコノリは国内全メーカーの全車種からお選びいただける、新車カーリースです。
新車の価格から契約期間終了時の車両の価値をあらかじめ差し引いた残額を、月々定額でお支払い頂くことで、新車にお安く乗ることができるようになっています。
その定額のお支払い額には、税金や点検や整備の料金、車検時などに必要となる費用などが含まれていますので、他に必要となるのは燃料代や駐車場代、任意保険代のみとなります。
ハイブリッドはいまも進化を続けている機構です。いまは最先端のシステムであっても、数年経つと旧式となってしまうことも考えられます。
そのとき、ニコノリなら、月々定額で新車にお乗りいただきながら、契約期間終了後は新たな車に乗り換えていだたくことも可能です。
もちろん、そのまま同じクルマに乗り続けていただくこともできます。
ハイブリッド車のことやカーリースのことなど、分からないことや不安なことがあればぜひお気軽にお問い合わせください。
>>ニコノリ安さの理由はこちら
>>カーリースできる新車はこちら
